
かつてプラスチックは、「土に還らないやっかいなものであり、かつリサイクルが難しく埋め立てて処分するもの」と認識されていました。
しかし今やこのような考え方は完全に時代遅れのものとなっています。現在は廃プラスチックのうちの80パーセント以上がなんらかのかたちでリサイクルにまわされていますし、廃プラスチックを新しく作り替える技術も発達してきています。
2022年には日本でも「プラスチック資源循環法」が施行されることになり、多くの人がプラスチックのリサイクルに関心を寄せています。
そしてそのような時流のなかで生み出されたのが、PCR(ポストコンシューマーリサイクル)とPIR(ポストインダストリアルリサイクル)です。
ここでは、このPCR(ポストコンシューマーリサイクル)とPIR(ポストインダストリアルリサイクル)を取り上げ、その特徴や違いについて解説していきます。
一般の消費者にとってもなじみ深い「PCR」

プラスチックの再利用を考えるうえで、非常に重要な単語として、「PCR(ポストコンシューマーリサイクル)」と「PIR(ポストインダストリアルリサイクル)」があります。この2つは対比して取り上げられることが多いものであるため、ここでもこの2つの特徴と違いについて解説していきます。
まずは、「PIR(ポストインダストリアルリサイクル)」の方から取り上げましょう。
PCR(ポストコンシューマーリサイクル)とは、使用済みのプラスチックを再利用すること
PCR(“post-consumer recycling”、ポストコンシューマーリサイクル。下記では、「PCR(ポストコンシューマーリサイクル)」の表記に統一する)は、「消費者が使った後のプラスチック製品を、廃棄することなく再利用すること」をいいます。
たとえば、ペットボトルのキャップやレジ袋を回収して、新しい製品にリサイクルしていくことがこのPIR(ポストインダストリアルリサイクル)にあたります。使用済みになったプラスチック製品を集めて、それを再加工することで、廃棄されるはずだったプラスチックに新しい道を与えるのです。
一般的に、PCR(ポストコンシューマーリサイクル)は以下の工程をとります。
- 1. まず、使用済みのプラスチック製品を回収します
- 2. プラスチック製品を、機械を用いて細かく砕きます
- 3. 廃棄物には汚れなどが含まれているので、それをすべて取り除きます
- 4. PIR(ポストインダストリアルリサイクル)気が残っている状態だとペレットの質が落ちるので、しっかり乾燥させます
- 5. プラスチックペレットに作り替えます
- 6. 5で作ったプラスチックペレットを利用して、新しいプラスチック製品を作ります
なお、PCR(ポストコンシューマーリサイクル)によって得られた素材は、ポスト・コンシューマー材(“post-consumer recycled material”、ポストコンシューマー材・PCR材とも。下記で「ポストコンシューマー材」の表記に統一する)と呼ばれます。ポストコンシューマー材はそれ単品で使われるのではなく、質を良くするためのポリエチレンなどを新しく混ぜ入れて製品に仕立て上げていくのが一般的です。
PCR(ポストコンシューマーリサイクル)で作られた「新しいプラスチック」はどうなるのか
回収されたプラスチック製品は、元の製品とまったく同じ物に加工されると決まっているわけではありません。回収されたプラスチックは、プラスチックペレットに加工されて、そのプラスチックペレットを使って新しい物を作り上げていくため、ペットボトルが釣り道具に変わったり、レジ袋が農業用のフィルムに変わったり、お菓子のパッケージがイスに変わったりします。
なお、PCR(ポストコンシューマーリサイクル)を行う場合、非常に大切なのが「もともとのプラスチック製品は、どのようなプラスチックで作られていたか」ということです。一言でプラスチック製品であったとしても、それがどのような種類のプラスチックで作られているかは製品によって大きく異なります。
たとえば、プラスチックのなかでももっとも多く使われていてシャンプーのボトルなどにも使われているポリエチレンは熱を加えることで柔らかくなるプラスチックですが、船舶などに使われているエキシボ樹脂などは熱を加えることで硬くなるプラスチックです。性質もまったく異なるからです。
出典:一般社団法人産業環境管理協会資源リサイクル促進センター「樹脂(プラスチック製品をつくるための原料)の生産」
PCR(ポストコンシューマーリサイクル)の持つ特徴について
PCR(ポストコンシューマーリサイクル)はPIR(ポストインダストリアルリサイクル)と比べて、その再生難易度が高いリサイクル方法だといわれています。
前述したように、PCR(ポストコンシューマーリサイクル)は「使用済みの」プラスチック製品を利用することになります。そのため、汚れが付着していることもあり、これを落とすための手順も必要となります。
また、現在はごみ収集段階での分別が非常に進んでいるものの、「同じプラスチック製品に見えるけれども、違うプラスチックで作られているもの」なども多数あります。これらを混ぜて加工してしまうと、プラスチックペレットの品質が著しく損なわれてしまうため、分別段階でしっかり分ける手間が必要になります。
選別にはさまざまな方法(遠心分離式選別や比重式選別など)を複数実施して取り組んでいくことになりますが、そのためには大きなコストや人手、機械が必要になります。
さらに、きちんと分別されていてさえも、組成の違いによる品質のばらつきが生じる可能性もあります。
このことを考慮して、エコマーク認定基準では、PCR(ポストコンシューマーリサイクル)とPIR(ポストインダストリアルリサイクル)の間に差を設けています。ポストコンシューマー素材の場合は再生プラスチック率が60パーセントで構わないとされていて、、PIR(ポストインダストリアルリサイクル)で得られた素材を使う場合よりも制限が緩いのです。
もっとも現在では、PCR(ポストコンシューマーリサイクル)を念頭に置いた新製品も開発されてきています。
従来型の「使い終わったプラスチック製品を、その組成や材質によって適したリサイクルに回す」というスタイルではなく、「初めからPCR(ポストコンシューマーリサイクル)用に開発した商品をリリースすることによって、PCR(ポストコンシューマーリサイクル)にかかるコストや人手などの負担を減らす」としたスタイルをとるところも多くなっているのです。
一般消費者が分類・分別を行いやすく、工場での仕分け段階でも作業が進めやすいこの「PCR(ポストコンシューマーリサイクル)を前提として開発された商品」は、今後のプラスチックリサイクルの世界において、非常に重要なものとなるでしょう。
PCR(ポストコンシューマーリサイクル)は、私たちの生活とも非常になじみ深いものであり、PIR(ポストインダストリアルリサイクル)に比べて意識しやすいリサイクル方法だといえます。
より無駄なく、難易度低く! PIRについて
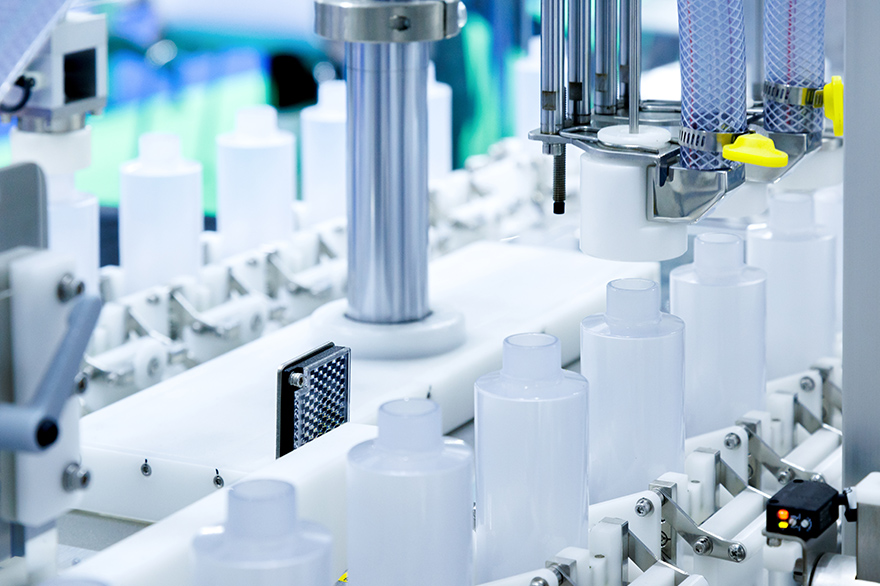
「工場内で出た端材を上手く使おう」が基本の考え方にあるPIR(ポストインダストリアルリサイクル)
PIR(“”post-industrial recycle””、ポストインダストリアルリサイクル。下記では「PIR(ポストインダストリアルリサイクル)」の表記に統一する)は、「製造過程で出た廃プラスチックを、再び製品のかたちにする」といいうものです。
どれほど素材を無駄なく使おうとしている工場であっても、またどれだけ素材のロスを少なくできる機械であっても、プラスチック製品を作るときには必ず「端材」が出ます。しかしこれらをそのまま捨てていては、環境の負荷も大きくなりますし、工場・企業にとってのコスト負荷も大きくなります。
そこで考え出されたのが、「PIR(ポストインダストリアルリサイクル)」という手法です。
PIR(ポストインダストリアルリサイクル)は、工場内リサイクルとでもいうべきものであり、工場内で出た素材をリサイクルのプラスチックとして使用することをいいます。最後まで無駄なく材料を使うために有効な手段であるため、この方法をとっている工場も多く見られます。
なお、「PIR(ポストインダストリアルリサイクル)」という単語を調べていると、しばしば「プレコンシューマーリサイクル」「プレコンシューマー材」という言葉に当たるはずです。
プレコンシューマーリサイクル(プレコンシューマー材)は、JIS(日本産業規格)における呼び方です。そのため、日本で使う場合は、PIR(ポストインダストリアルリサイクル)とプレコンシューマーリサイクルおよびそこから得られるプレコンシューマー材は、ほとんど同じ意味だと考えてよいでしょう。
PIR(ポストインダストリアルリサイクル)の特徴、PCR(ポストコンシューマーリサイクル)との違いについて
PIR(ポストインダストリアルリサイクル)とPCR(ポストコンシューマーリサイクル)とのもっとも大きな違いは、「PIR(ポストインダストリアルリサイクル)は、PCR(ポストコンシューマーリサイクル)とは異なり、一般のユーザーにはほとんど意識されない」という点です。
PCR(ポストコンシューマーリサイクル)は一般消費者自身が出したゴミを洗浄―分別―回収に出すという段階を踏むため、非常に理解をしてもらいやすいものです。
しかしPIR(ポストインダストリアルリサイクル)は工場内で完結されるものであるため、(そこで作られたプラスチック製品が一般消費者の手元に届くことはあっても)一般消費者が直接見る機会はほとんどありません。
さて、このような特徴を持つPIR(ポストインダストリアルリサイクル)には、一般消費者の手を経ないからこそのメリットがあります。
まず、PIR(ポストインダストリアルリサイクル)の場合は選別の手間が非常に少なくなります。なぜなら原材料となるプラスチックは工場内で作られているもので、「ほかのプラスチック製品と混ざってしまう恐れ」がほとんどないのです。また、汚れを取り除くことも容易です。さらに組成が一定であるため、リサイクル後の製品の品質も安定しています。
総じて、PCR(ポストコンシューマーリサイクル)よりもPIR(ポストインダストリアルリサイクル)の方がコスト・手間の負担が少ないものだといえるでしょう。
このような特徴を持つPIR(ポストインダストリアルリサイクル)は、エコマーク認定基準が厳しく設定されています。PIR(ポストインダストリアルリサイクル)で得られたプレコンシューマー材を使用する場合、再生プラスチックの割合が70パーセント以上でなければこれを受けることができません。
PCR(ポストコンシューマーリサイクル)とPIR(ポストインダストリアルリサイクル)は、プラスチック製品のリサイクルを考えるうえでは、知っておかなければならない単語・仕組みだといえます。
ただ、PCR(ポストコンシューマーリサイクル)とPIR(ポストインダストリアルリサイクル)にはそれぞれその方法や考え方に違いが見られます。コストや手間のことを考えればPIR(ポストインダストリアルリサイクル)に軍配が上がりますが、だからといってPCR(ポストコンシューマーリサイクル)をないがしろにしてよいということではありません。消費者によって出される大量のプラスチック製品が、PIR(ポストインダストリアルリサイクル)を経て、新しいものに生まれ変わることは環境負荷の軽減に直結しているからです。
私たちベストプラでは、プラスチックのリサイクルを通じた環境負荷の軽減に取り組んでいます
 お問い合わせはこちらのお問い合わせフォームまたはお電話でどうぞ
お問い合わせはこちらのお問い合わせフォームまたはお電話でどうぞ
電話番号: 0267-22-2268






